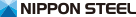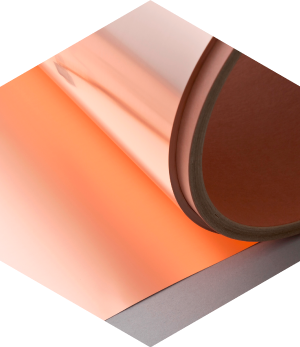当社は、社員が生活との調和を図りながら職務に精励し、もてる能力をいかんなく発揮できるようにすることが、個々人の活力向上や会社全体の労働生産性向上に資する、との考えのもと、多様な人材・働き方を受け入れる施策として育児・介護関連制度の拡充を図っています。
仕事と育児との両立支援への取り組み
「次世代育成支援対策推進法」に基づく優良な「子育てサポート」企業として、厚生労働大臣より「くるみんマーク」の認定を受けております。
今後も、「出産・育児に関する社内外制度の周知・啓蒙や職場の理解活動を進め、仕事と家庭の両立に資する育児関連制度の活用を促進する」ことや、「子育てを行う社員が活用しやすい育児休業または勤務措置等の制度検討、充実を図る」こと等に積極的に取り組んでいきます。
今後も、「出産・育児に関する社内外制度の周知・啓蒙や職場の理解活動を進め、仕事と家庭の両立に資する育児関連制度の活用を促進する」ことや、「子育てを行う社員が活用しやすい育児休業または勤務措置等の制度検討、充実を図る」こと等に積極的に取り組んでいきます。

仕事と育児の両立支援制度
| 制度名 | 内 容 |
|---|---|
| 産前・産後休暇 | 出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から出産後8週間まで取得可。【無給】 |
| 配偶者出産休暇 | 配偶者の出産当日前後10日以内(出産当日を含む)に通算2労働日まで取得可。【有給】 |
| 子の看護休暇 | 小学校6年生修了前までの子の病気やケガの世話および予防接種や健康診断受診のために、子どもが1人の場合は当該年度につき5日、2人以上の場合は10日取得可。【無給】 フレックスタイム制適用者は1時間または1日単位、交代勤務者は半日または1日単位。 |
| 福祉休暇 (※年休取得残の積立休暇) |
不妊治療や女性特有の事由(妊娠時の体調不良、妊産婦健康診査の受診時)および中学校卒業までの子の養育(子の看護、通院、学校行事への参加)、育児休業および出生時育児休業への充当において取得可。【有給】 |
| 育児休業 | 1歳6か月(保育所に入所できない等の特別な事情がある場合は最大3歳)に達するまでの子を養育するために、2回に分割して取得可。【無給※ただし子が1歳に達するまでは雇用保険から給付金が支給(特別な事情がある場合は2歳まで受給可)】 |
| 出生時育児休業 | 産後休暇を取得していない社員が、原則出生後8週間以内の子を養育するために最大4週間(28日)まで取得可。【無給※ただし要件を満たせば雇用保険から給付金が支給】 |
| 在宅勤務制度 (※育児・介護・治療型) |
小学校修了前までの子を養育する社員は、10回/月(+部分在宅勤務2回/月)実施可。 |
| 育児のための勤務時間措置 | 満1歳に達しない子を養育する社員は、育児時間(2回/日 各々30分間)の措置を受けることが可。 |
| 小学校3年生修了までの子を養育する社員は、所定外労働の免除、始終業時刻の繰上げ・繰下げ、深夜就業の制限、法定時間外労働の制限の措置を受けることが可。 | |
| 小学校6年生修了までの子を養育する社員は、短時間勤務制度、フレックスタイム制、フレックスタイム制のコアタイム変更の措置を受けることが可。 | |
| キャリアリターン制度 | 勤続3年以上の社員が、当社で働く意思があるにも関わらず、出産・育児等でやむを得ず退職した場合は、事情解消時に所定の手続きを行うことで再入社が可。 |
仕事と育児の両立支援施策
| 仕事と育児の両立支援ハンドブックの配布 | 当社の育児関連制度の概要や業務引継ぎ、上司との面談等を纏めたハンドブックを社員版と上司版それぞれ発行。 |
|---|---|
| 育児社員向けの座談会 | 長期休業から復帰した社員や、男性社員、育児休業中の社員を対象に座談会を開催。 |
| 仕事と育児の両立支援セミナーの開催 | 1回/年に、上記のハンドブックを活用し社員および管理職それぞれに対し制度説明のセミナーを開催。 |
| 社内ポータル | 社内ポータルを通し、ハンドブックの電子版やセミナーアーカイブ配信、社員ヒアリング内容等を掲載。 |
情報公表
※出生年度と休業取得年度が異なる社員もおります
育児休業取得率 (男性社員)
- (2024年度実績) 67%
- (2023年度実績) 59%
- (2022年度実績) 58%
男性の育児休業等と育児目的休暇の取得割合
- (2024年度実績) 93%
- (2023年度実績) 94%
- (2022年度実績) 93%
育児休業取得率(女性社員)
- (2024年度実績) 100%
- (2023年度実績) 89%
- (2022年度実績) 129%
仕事と介護の両立支援制度
| 制度名 | 内 容 |
|---|---|
| 介護休暇 | 要介護状態等にある対象家族の介護のために、対象の家族が1人の場合は5日、2人以上の場合は10日取得可。【無給】フレックスタイム制適用者は1時間または1日単位、交代勤務者は半日または1日単位。 |
| 福祉休暇 (※年休取得残の積立休暇) |
要介護状態等にある家族の介護(入院中の身の回りの介護、リハビリ・通院介助、在宅看護を行うにあたっての受け入れ体制の整備等)のために取得可。【有給】 |
| 介護休業 | 要介護状態等にある家族を有する社員について、最大1年間取得または累積93日以内の介護においては介護対象者1人につき歴日1年を越えて回数の制限なく取得可。【無給※ただし雇用保険から給付金が支給】 |
| 在宅勤務制度 (※育児・介護・治療型) |
介護(要支援以上)を必要とする家族を有する社員は、10回/月(+部分在宅勤務2回/月)実施可。 |
| 介護のための勤務時間措置 | 要介護状態の対象家族を有する社員は、短時間勤務制度、フレックスタイム制、所定外労働の免除、始終業時刻の繰上げ・繰下げ、深夜就業の制限、法定時間外労働の制限、フレックスタイム制のコアタイム変更の措置を受けることが可。 |
| キャリアリターン制度 | 勤続3年以上の社員が、当社で働く意思があるにも関わらず、介護等でやむを得ず退職した場合は、事情解消時に所定の手続きを行うことで再入社が可。 |
| 介護のための交通費補助 | 介護のための交通費(公共交通機関および私有車輛利用の場合)が1回につき1万円を超える場合は、1万円を超える部分につき、3万円を上限に実費を交通費補助として支給。 |
| 介護に関する相談窓口 (外部) |
法人契約をしている「NPO法人 海を越えるケアの手」のサービス(無料相談、会社主催セミナー、代行サービス(有償))を受けることが可。 |
仕事と介護の両立支援施策
| 仕事と介護の両立支援ハンドブックの配布 | 制度の概要や介護保険等についての説明、チェックシート等を纏めたハンドブックを発行。 |
|---|---|
| 仕事と育児の両立支援セミナーの開催 | 当社が法人契約をしている、「NPO法人 海を越えるケアの手」に講師を依頼し、3回/年、介護セミナーを開催。 |
| 社内ポータル | 社内ポータルを通し、ハンドブックの電子版やセミナーアーカイブ配信等を掲載。 |